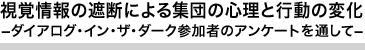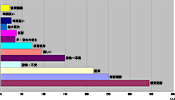![]()
Behavior and Mentality Alteration by shut out Visual Information under the Perfect Darkness. -Through the Impression sheet written by participants of the Dialog in the Dark Showcase in Kobe.-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以下、DIDと略記)はドイツのハイネッケ博士が1989年に考案した体験型イベントで、光を完全に遮断した空間を形成することで、視覚刺激を無くし、視覚以外の感覚を使っての体験を言う*1。暗闇の中には日常生活のさまざまな環境が盛り込まれており、参加者は小集団で全盲の人の案内に導かれて非日常の暗闇を体験する。DIDの詳細に関しては、これから体験する参加者のために明らかにすることはできないが、障害体験プログラムではなく、暗闇を楽しむ体験型ワークショップであり、福祉的意味合いを持ったものではないことを明記しておく。
著者らは、2005年8月17日から25日の9日間、神戸市中央区港島中町のジーベック・ホールにてDIDショーケース・イン神戸を開催し、743名の参加者を得た。参加者の多数は体験終了後のアンケート用紙に思い思いの感想を書き込んだ。この報告は、これらの参加者が残した感想をもとに、視覚情報が遮断された環境における集団の心理と行動の変化について述べたものである。なお、イベントの内容を具体的に伝えるような記述はできないため、感想の一部は削除している。
DIDは1999年に横浜で第1回が開催されてわが国へ紹介された。その後、2000年に神戸、2001年に仙台で開催され、2002年からは毎年東京で開催されてきた*2。このほか、小規模なイベントとして各地でDIDショーケースが開催されており、2005年の神戸は第8回目のショーケースとして、特定非営利活動法人DIDジャパン(代表:金井真介)の監修の下で開催した(図1)。会場のジーベック・ホールは2000年のDID会場でもあり、ショーケースとしては大規模なイベントであった。運営には学生を中心としたボランティア・スタッフが携わり、会場内を誘導案内するアテンド・スタッフには神戸や大阪在住の視覚に障害のある人たち8名が参加した。参加者は7名ずつのパーティーを組み、視覚に障害のある人が使用している白杖を手に持ち(図2)、アテンド・スタッフの声に導かれて暗闇を探査した(図3)。ガイダンスから終了までの所要時間は1時間程度であった。暗闇から出たところには休憩用のテーブルと椅子を用意し、机上にはスケッチブックとパステルなどの画材およびアンケート用紙を置いた(図4)(図5)(図6)(図7)。特にアンケート用紙への記入を求めたわけではないが、大多数の参加者が密度の濃い感想を残した(図8)。
抽出したキーワードは、「障害への理解」、「感覚覚醒」、「連帯・協力」、「恐怖・不安」、「楽しい」、「不安から楽しくなった」、「能力喪失」、「視覚依存」、「時間長く感じた」、「時間短く感じた」、「新鮮」、「不思議」、「空間認識」、「声や音の大切さ」などであった(図9)。主要な感想としては、次の3点に集約された。
1) 感覚覚醒 345名 47.3%
2) 障害への理解 251名 34.4%
3) 連帯・協力 215名 29.5%
3-1 感覚覚醒
感覚覚醒は75%以上とされている視覚刺激が遮断されることによって、聴覚、触覚、嗅覚および味覚に関して普段よりも敏感になったという記述が多く、聴覚による音源の定位ができることへの感動や、触角から形態の記憶を呼び起こすことの発見などがあげられた。また、床面の状態を知るために足裏感覚が敏感となることや、視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)の有用性を理解したという記述が多くみられた。味覚に関しては、イベントの中で供される飲料に対して、より美味しく感じたという意見と、見えないと味がわからないという両方の意見が見られた。
感覚覚醒を目的として参加した人一部の人は、アテンドの声による誘導やパーティー・メンバーの声などをうるさく感じ。暗闇の中に一人でじっとしていることを期待したようだった。
感覚覚醒に関する書き込みにかかわらず、声の大切さや音の大切さを記述したひとは多く(34名)、日常視覚に依存していることを実感した人は73名いた。
3-2 障害への理解
障害への理解は、自らが視力に頼ることができない環境に置かれ恐怖や不便を感じたことから、視覚に障碍のある人の不便さを理解する人と、暗闇の中で見えているかのように行動できる全盲のアテンドに対して、「弱者としての障害者」という偏見に気づく人とに大きく分けられた。目が見えないと困るというマイナス体験は、広く行われているアイマスク体験などでも可能であるが、プラス側の体験はDIDでないと直感できない。参加者の中には、イベントが終了し光のある世界に戻ったときに、アテンドの人との違いに再び気づき、明かりの中でアテンドの人との距離を急に感じたという感想を記した人もいた。また、手に触れたものに対して、記憶から形状や色彩をイメージするプロセスを楽しんだという人もいたが、生下時から視覚に障害のある人は色彩や形状をどのようにイメージするのだろうかと疑問を投げかけていた。知識としての「見えない人」という理解から、体験を通すことでより深い理解へ、あるいはより深く相手を知ろうとする態度の変化が感想の中に見られた。
光という環境条件が変化することで、視覚に頼っている人と視覚に頼っていない人の立場は容易に逆転することに気付くことができる。「障害者」が常に弱者であるのではなく、環境との適合として障害が存在していることに気が付く。DIDこそ障害に対する正しい理解を得ることができる装置である。
3-3 連帯・協力
不安で一杯の暗闇の中で、パーティーの存在は心強いものになる。友人や家族と一緒に参加した人も多いが、会場で始めて出会った人達とパーティーを組んで参加した人も多い。初対面でも気軽に声をかけあったり、助け合ったり、身体の一部が触れ合うことで安心したりできることが不思議であり、喜びであるという感想が多く寄せられた。互いの顔が見えないことがコミュニケーションを促進させ、安心させると考えられた。また、常に一方的に見られる存在に置かれている視覚に障害のある人の心中を思いやる意見や、視覚に障害のある人に電車の中で声をかけられたことの意味(傍に居る人がどのような人かを理解しておきたい)を理解できたという感想も印象的であった。
見ず知らずの人達がお互いに助け合い、協力しあう関係に容易になれることは、視覚情報が遮断されたことによる能力喪失を相互に理解することによると思われる。これは、震災などの大規模災害時に被災者同士が助け合うことと共通するものと考えられる。このような体験を身近にできることは、DIDの大きな効用といえ、より多くの人々とりわけ子供たちに経験させたいという意見が多数残された。
3-4 その他
暗闇の中に入ったときに不安や恐怖を感じたという人は、196名(27.4%)いたが、このうちの149名(20.4%)は時間の経過とともに楽しめたと記述し、終わるまで不安だったと記述した人は47名(6.5%)だった。最初から楽しめたという96名をあわせると245名(34.2%)は「DIDを楽しんだ」と積極的に記述した。これは、DIDが福祉的イベントではなく、エンタテインメントであるとする主催者側の意向が参加者にも伝わった結果といえる。
最初から楽しめたと記述した人は、「心がほかほかする」、「見えないことの楽さを感じた」、「開放感」、「妙な安心感があった」、「見えないことがプラスに働く」といった感想を記述していた。
暗闇の中での時間経過に関しては、具体的に長く感じたり(25名)、短く感じたり(2名)したと記述した人は少なかった。同様に空間認識に関して具体的に記述した人は21名にすぎなかった。
DID参加者の感想をもとに、暗闇の中におかれた集団がどのような影響を受けたかを調べた。自由記述の感想文を調査の対象としたため、集計項目の件数が少なくなったが、調査者側の意図に偏らない参加者の本音が寄せられたと思われる。記述の多くは、もっとも印象の強かった項目数点に集中しており、時間認識や空間認識に関しては設問を用意していればより多くの回答が寄せられたと推測できる。
「DIDのことを誰かに伝えたいか」というアンケート項目にはほぼ全ての回答者がチェックをいれ、「誰に伝えたいか」の質問に対して、友人や家族といった近親者に加えて、子供たちという記述が多かった。感受性の豊かな子供たちがDIDを経験することで、他人に対する思いやりの心や、多様性に対する理解を深め、コミュニケーションの大切さを自然に学ぶことができると期待される。神戸市では2000年に続いて2回目の開催となったが、常設化に向けて動き出している。DIDが常設化されれば、視覚に障害のある人が自らの特性を生かせる雇用機会を創出することにもなり、多様性の理解と相手の立場にたって考えるというユニバーサルな社会づくりに重要な教育を、楽しみながらできる場を提供することにもつながる。
本稿をまとめるきっかけとなったDIDショーケース・イン・神戸の開催に当たっては、本学の古川圭子、中村正美(当時)、藤田可奈子、上松孝瑞、山内真一、他多数の学生諸氏、アテンドに応募いただいた小野耕一氏、小山田みき氏、北村多恵氏、小寺洋一氏、中部秀樹氏、原口淳氏、久部幸次郎氏、三上洋氏、森嶋ちさと氏らに献身的な協力をいただいた。また、神戸アイライト協会には白杖の提供と使用方法の教示をいただき、ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンの金井真介代表およびスタッフの方々には熱心な監修ならびに運営指導をいただいた。最後に、神戸市、株式会社フェリシモ、および塩井障害者自立支援基金には資金援助をいただいたことをここに記して謝意を表す。
注・引用文献
| *1― | ダイアログ・イン・ザダーク・ジャパン公式サイト、http://www.dialoginthedark.com/contents/whats_did/index.html |
|---|---|
| *2― | 金井真介[DIALOG IN THE DARK]特定非営利活動法人ダイアログ・イン・ザ・ジャパン、2004 |
* Dialog in the Darkおよびダイアログ・イン・ザ・ダークはDr. Andreas Heineckeが著作権者であり、特定非営利活動法人ダイアログ・イン・ザ・ジャパンが国内での一切の再使用権を有しています。