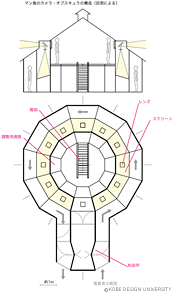![]()
Research of the Camera Obscura
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
現代社会において、視覚映像が人間相互のコミュニケーション手段として果たす役割は年々増大し続けている。人々が日常生活の中で目にする映像は、映画、テレビ放送、インターネット画像など多種多様な展開を見せている。これほど人類に広範囲な影響力を与える視覚映像が発達したのは、写真技術がその基盤にあったためである。写真技術はLouis-Jacques-Mandé Daguerre がダゲレオタイプ(銀板写真術)を発明し、1839年にフランス科学アカデミーで発表したことによって世界に広まった。その後、ネガ・ポジ方式や感光材料の改良によって取り扱いが徐々に簡便になり、現在の写真の隆盛に至っている。さらに近年、デジタル写真の登場によって革命的な変貌をとげ、写真映像が日常生活の中に溢れるようになった。
ここまで驚異的に発達してきた写真技術開発の推進役を担ったのは、ヨーロッパ文明の中で長い年月に渡って使用されてきたカメラ・オブスキュラという視覚装置であるとされている。カメラ・オブスキュラとはラテン語で暗い部屋という意味である。建造物の壁に穿たれた小さな穴やレンズを通した光が暗い部屋の内部に導き入れられ、外部の光景を壁に写し出して見る装置のことである。
紀元前4世紀ギリシアのアリストテレスにより、すでに原始的な暗室の形は発見されていたとされる。小さな穴を通して暗い密室に光が差し込むと、穴の向かいの壁面に外の風景が倒立逆像で現れる現象は、遅くとも2000年前から各時代、アリストテレス、ロジャー・ベーコン、レオナルド・ダヴィンチなどさまざまな思想家、科学者、画家などによって経験的事実として認識され、考察され、書き記されてきた。その内容は主に人間の視覚との相違について、である。人間が使用した最初期の視覚装置であるカメラ・オブスキュラは、暗い部屋の内部に人が入って外界の光景を見るための建築空間であった。発見されて以来永らくは、直に見ることが危険な太陽の観察、例えば日食の経過確認などに大いに利用されたらしい。カメラ・オブスキュラは次第に世界を見る絶対正確な視点と見なさるようになったが、絵画に用いられるのはルネサンスの自然科学復興以後である。ルネサンス時代には、持ち運び可能な箱形のカメラ・オブスキュラが製作されており、画家がこの視覚装置を使用して絵を描いていた。次第に明るく鮮明な像を求めてレンズや絞りの取り付けといった改良が加えられ、文献資料を見ると様々な用途に応じた多くの携帯可能な視覚装置が存在したことがわかっている。遠近法の発明はカメラ・オブスキュラを使用した絵画の制作と深く関係している。
18世紀、産業革命と旅行の大流行の時代には、科学者や画家だけでなく一般の人々も携帯オブスキュラを持って旅をしては、風景を描き写しとる行為に夢中になる。暗い空間の内部で明るい外の光景を覗き見るための、こうした視覚装置は写真発明のきっかけを創った。1839年、像を科学的に銀板に定着する写真術がダゲールによって発明されると人々は眼鏡店(光学機材を扱う店)に押し掛けて撮影機材を買い求め、たちまちトレースによる絵画制作の熱は下がり、代わりにカメラと写真撮影が普及していく。
カメラ・オブスキュラ内部に投影される映像は、その時その場限りでしか見られないが、映像を感光材料によって物質化し固定することによって過去の光景を見ることが可能となり、映像を移動させて別の場所で見ることも可能となったのである。カメラ・オブスキュラは、今日我々が使用している写真、映画、ヴィデオ撮影用カメラの原型となるものである。
こうしたカメラ・オブスキュラの現状を調査するため、2006年9月、英国EdinburghとIsle of Manに現存する施設を訪ねた。
2-1.Outlook Tower(Edinburgh, Scotland)
英国北部Scotlandの都Edinburghは、小高い岩山にそびえる王城を中心とした歴史のある古い都市である。丘の上の城へと続く石畳の通りには多くの飲食店や土産物店が並び、春から秋にかけてのシーズンは観光客であふれている。この城の手前に位置する見晴らしの良い場所にあるのが、Outlook Towerと名づけられたカメラ・オブスキュラである。
この装置は1856年に完成し一般公開された。さらに1947年に解体修理して性能を向上させ現在にいたっている。(*1)
カメラ・オブスキュラは小高い丘に位置する古城を模した5階建てビルの屋上にあり、間近に見える王城を含めて素晴らしい眺望の場所である。古都Edinburgh の旧市街をほぼ全て見渡すことができる場所を選んで設置したことがわかる。英国有数の観光都市の最も眺めのよい場所から、カメラ・オブスキュラを通して改めて眺望を楽しむための装置である。
ドーム状の天井屋根の上にレンズが取り付けられており、鏡により真下に投影される外部からの光は部屋の中心にある円盤状のテーブルに写される。レンズは風景が遠近にズームされ360°回転する。円盤テーブルの周りに観客席が2段に設けられており、およそ2~30人の観客が囲むようにして鑑賞する。
観覧時間は一回約30分間。弁士が天井のレンズから伸びる操作棒で角度や遠近を操りながら行われ、巧みな語り口で面白おかしく語る様は、さながら無声映画を弁士付きで鑑賞しているようである。
しかし映画館で見る映画の映像とは異なって、投影されている映像は同時刻の外部の光景である。観光地の眺めではあるが、とりたてて特別な出来事が起こっているわけではなく、いたって日常的な街の眺めである。先ほどまで歩いていた街路の光景が暗い闇の空間に投影された映像として眺めてみると、現実の光景をどこか遠い別の世界から眺めているような不思議な感覚に襲われる。
それは高い建物の屋上から望遠鏡で地上の街路を眺めることとは明らかに異なる。望遠鏡で見える像が身近に引き寄せられて拡大することはあっても同じ空の下での、あちらとこちらという連続感は失われていない。ところがカメラ・オブスキュラで写される光景を眺めていると、同じ空の下での連続した空間での映像という感覚は消え去り、まったく別の世界から眺めているという感慨に浸ってしまう。このことは、暗く閉ざされた闇の空間の中に写された映像を見ているということと、映像があたかも光による物体と化したかのように、テーブル上に手で触れるように在るということがあるのかもしれない。実際、弁士が白い紙を取り出してテーブル上の映像に差し出し、紙の上に部分的に写った映像と戯れて遊ぶようなことをして見せてくれる。
カメラ・オブスキュラによって投影された映像を、感光材料によって固定化したのが写真である。そのことによって白日の下で映像を見ることを可能にし、物体となった映像を手にすることも可能になった。だが、そうして獲得された今日の写真映像以前には、現実そのものではないけれど闇に投影された、もうひとつの生な現実もどきの映像と人々は遊び戯れていたに違いない。
Outlook Tower は、Edinburgh という城を中心とした観光都市を訪れる多くの観光客のために建設されたカメラ・オブスキュラである。丘の上から肉眼で直接に街を眺めることとはまた違う、異なる次元の映像を眺める装置が現役で運営され今日まで存続していることは実に貴重である。
2-2.Edinburgh のカメラ・オブスキュラの変遷~Short 家が設立した天文台
Edinburghの商人、Thomas Shortが建設に貢献した天文台は、Edinburgh大学の光学研究を支援するため、望遠鏡をイギリスで入手して持ち帰ったところから始った。当時、イギリスの天文学は王立天文学協会を中心に隆盛期にあった。特にNewton以来関心が薄れていた反射望遠鏡が、1720年以降再び注目されていた。
Thomas Shortの兄、James Shortは1732年、望遠鏡制作に没頭するあまり、Scotland教会の牧師の地位を捨ててLondonに移住した。彼の制作はもっぱら鏡の部分であり、望遠鏡の本体は下請けに出して精密な金属鏡の制作に打ち込んだ。彼の作った望遠鏡はグレゴリー式といわれる比較的小型の正立像が見えるタイプで裕福なアマチュア天文学者などに大いに好まれ、天才的な職人として人気を誇った。これをEdinburghに持ち帰ったのが、James Shortの弟で、当時、光学レンズを扱う眼鏡商を営んでいたThomas Shortである。
2-3.Calton Hill の天文台(この第3 項はエジンバラ天文学協会のウェブサイトを転載、和訳したものである(*2))
1776年、EdinburghのLeith出身の眼鏡商、Thomas Short氏が亡くなった兄のJames Shortが作った12フィートの反射望遠鏡を、ロンドンから持ち帰り、これを設置した天文台が、Calton Hillの上に建てられた。安い入場料で人々に公開されるパブリックの天文台であった。実はこれより35年前から、Edinburgh大学の学生の研究のための望遠鏡を設置する目的でEdinburgh大学の数学教授Colin Maclaurinと、Shortによって天文観測所設立の資金は用意されており、Calton Hillに半エーカーを99年間の借地許可も得ていたのである。
天文台は、当時、新市街建設もしていたJames Craigによって設計され新市街建設と同年に開始された。およそ48フィートの八角形のタワーで東西に別棟も建つ予定だったが、建築家Robert Adamが銃眼と扶壁のある要塞のような外観を提案したことにより一角の壁が建った時点で資金が底をついてしまい、そのうちEdinburgh町評議会も天文台建設には興味を失ってしまった。結局、Shortは、天文台の建物の丸いタワーの部分を個人宅にし、付随する天文台は小さなものになった。(図4参照)
1788年にShortが世を去ると、天文台の権利は孫のJames Douglasに渡り彼は1日2シリングで人々に天文台を公開した。ところが、Short 未亡人が反射望遠鏡の鏡などを天文台から運び去ってしまい、Short未亡人と孫のJames Douglasの間に、所有権争いが起こる。望遠鏡などの設備を取り戻すためにJames Douglasは多額の支払いを要求され、さらにShortの子どもたちは天文台から立ち退くよう礼状が出された。Short未亡人は使用人たちとともに短剣、ピストル、短銃で武装して天文台の自宅に戻ろうと押し掛け、警察によって拘束された。孫のJames Douglasは破産して去った。その後天文台の建物は1807年に火薬店になるまで、眼鏡商一族の手から手へ渡っては寂れていった。
Calton Hillの天文台とShort家の関係は1827年になって復活した。この時すでに唯一Thomas Short氏の血を継ぐ娘であったMaria Theresa Shortが西インド諸島から戻ってきたのである。天文台はEdinburgh大学の天文学協会の管理下におかれていたが、Maria Theresa Shortは自身に天文台分与の権利があることを知った。彼女は反射望遠鏡を再び設置することに成功し、彫刻家Robert Forrestの作品のある国立記念碑の近くに、木造の天文台を建設する許可を得た。3つのパワフルな望遠鏡、そして単眼式のカメラ・オブスキュラなどが、天文台の広告塔となった。しかし、新たな天文台設立に反対する者たちから「粗悪な科学館」、「人々を煽る下品な見世物」と不平の声があがった。やがて町議会も「不快で不格好な」天文台の閉館を要請した。市民から4000もの保存嘆願の署名があったにも関わらず、1850年にMaria Theresa Shortは立ち退きを余儀なくされた。天文台は破壊され、設備はぞんざいに地面に投げ捨てられた。彼女は公開天文台を存続するため、貴重な機材とともに、Edinburgh城に近い古い建物に移る事を余儀なくされた。それが現在のカメラ・オブスキュラ館付き視覚美術館、Outlook Towerである。(図1参照)
2-4.視るものと視られるもの
Edinburgh城のある高台Royal Mileに建つ、Outlook Towerの屋上に階段でのぼり、カメラ・オブスキュラに入って、卓上に映し出された街の風景を見るときに得られるのは、多くの観光客が、ジオラマをさまよう人形のように掌の上を歩き、中の人々の生活をドールハウスのように覗きこんでしまう巨視と接視の共存、神の視点から「窃視」するような不思議な感覚である。古い石造りの街の中にひときわ古く窓が少ない要塞のような館が見える。面白いことにそれはこのオブスキュラを作ったShort家の館であり、オブスキュラから不特定多数の人々がこうして市街を見渡し家々を覗き込むことを予測していたのである。
2-5. Great Union Camera Obscura(Douglas Isle of Man)
England とIrelandの間のIrish海に浮かぶ、オートバイ・レースで有名なIsle of Manの表玄関がDouglasである。Douglas はEngland本島との間を行き交うフェリーの発着する港町であり、海岸道路沿いにリゾート・ホテルが建ち並ぶVictoria女王時代に繁栄した、いわゆるVictorian Cityである。海岸沿いに広々とした遊歩道が続き、建築高がきれいに整った白いホテルが建ち並ぶ様は、Victoria時代の優雅なリゾート地の雰囲気を今なお色濃く残している。
Great Union Camera Obscuraは、そうした港町を望む小高い丘の中腹に建てられている。急傾斜の丘の斜面からは、遊歩道に沿って建ち並ぶホテル群が左手に一望できるし、港に出入りするフェリーも視界に入ってくる景勝地である。右手には灯台のむこうにIrish海が広がっている。このカメラ・オブスキュラも、こうした眺望の素晴らしい観光地の風景を眺めるために建設されたことがわかる。
20世紀初頭にはポストカードになって紹介されているところを見ると、観光客相手の人気スポットであったようだ。汽船が多数入港していて賑やかな港町を望むGreat Union Camera Obscuraに人々が群がっているのが見てとれる。(*3)
このカメラ・オブスキュラの他に類を見ない最大の特色は、何と言ってもその独特の内部構造にある。外観は円形で屋根は円錐型、ロマンチックな世界と出会えそうな雰囲気のお伽話風な造りの木造建築である。建物内部には円く回遊する通路が出来ており、中心から通路側に向けて11個の台形ブースに分かれた白いテーブル面に投影された風景をグルリと歩きながら見て回るのである。回遊式カメラ・オブスキュラである。
角度30度分ずつ12個あるはずの一つは、入り口であるために11個の画面となっている。画面それぞれの上部にはレンズが組み込まれており、屋根の上にはレンズ小屋が取り付いている。写る風景が各ブースによって違うので焦点距離をブース毎に変えてあるなど、実に手の込んだ仕掛けの見せ物小屋である。中心部裏側のコントロール・ルームは素朴な木造りの仕掛けがいっぱいあって、木綿の紐でレンズの蓋を開けたり調節したりと、この見せ物小屋は緻密に組み立てられた一品製作の工芸品であると同時に独創的な設計者による建築作品である。
天井から台形ブースに投影された風景は観客の背中にあたる建物外の風景だが、逆方向の内側中心に向かって眺めることになる。いままで外で見ていた風景が逆転して、円の中心に向かって内側に並んでいるのである。まずここで意識が少し変わってきて、つい先程見ていた同じ風景を見ているとは思えない気分となる。
台形テーブル上に見える映像は、港に停泊する船や海岸遊歩道路沿いに建ち並ぶ白いリゾートホテルなどである。打ち寄せる波の動き、風にはためく国旗、歩道を散歩する人々などと、取り立てて物珍しい風景ではないのだが、その一つ一つの動きに見とれてしまう。暗闇の中のブースで仕切られたスペースという限定空間に投影された現在の映像であるため、生き物のように生々しくキラキラと輝いて見える。空が晴れた日は青空が写り天気の悪い日は曇り空と、天候や日照時間の影響を直接受けるため、現実の風景との一体感は特別である。同じ場所で在りながらもその日のお天気次第で、いろいろな光景に変化してしまうのである。映画やヴィデオ映像とは根本的に異なる体験である。
このGreat Union Camera Obscuraは、天井レンズ室の鏡で反射させた複数の風景正立像を円形に並べ観客を回遊させて鑑賞させるという、光学系と建築設計を絶妙に組み合わせた視覚映像装置の傑作である。こうした記念碑的な建築がVictoria 時代のリゾートホテル街を望む丘の上にひっそりと佇んでいるのである。
2-6.パブリック・カメラ・オブスキュラと視線の民主化
つまり、一般人に娯楽として提供されたパブリック・カメラオブスキュラは膨大な観察者たちの遺産によって作られたスペクタクルのひとつなのである。人々は、カメラ・オブスキュラによる視覚の客体化から解放される時代になって、部屋型オブスキュラで暗室の最後の光を共有して楽しんだのかもしれない。同時に携帯小型オブスキュラ(カメラ)は次々に改良され、そこに映し出された像はすべて痕跡(写真)となって複製され、市民に行き渡っていった。情報、保存、複製というメディア(媒体)の大進歩のただ中にありつつ、人々はさらに視線の共有を望んだ。
ヨーロッパ19世紀に建設された数多くの塔や、熱気球で高みにのぼるのは、もはや神に近づく行為ではなく、人間が上からすべてを眺めるまなざしを得るためであった。そこで得られる眼差しは、たとえば遠近法に基づいたルネサンス絵画やバロック絵画のように、視る為の正位置が定まっていたイメージと異なり、市民の無数の眼が平等に目の保養が得られる「散漫さ」を持っている。つまり視線の民主化である。娯楽施設としてのステレオスコープやパノラマ館、そしてカメラ・オブスキュラ館は、見渡す行為に不慣れな大衆の不安や恐れをさらに払拭し、人々に眼差しの解放を押し進めていった。(*4 )しかし、その解放は、人間が人間を視線によって統制、支配するという表裏一体の進歩であることは、後の章で述べる。
2-7.イメージの所有
イギリスに限らず、世界のパブリック・カメラオブスキュラの多くは高台や海辺、岬などに作られている。展望が良い風光明媚なロケーションであり人々が余暇を楽しむ場所である。リゾートを楽しむ場所に至るまでの鉄道で移動し、密室から車窓の風景を楽しみ、旅先ではわざわざ狭くて暗い小屋に入って外界を覗き視るように眺める。雄大な自然はレンズを通して切り取られ卓上に置かれた鳥瞰図、または箱庭のようである。19世紀の視覚は常に、旅と密室、移動と所有が共存し、追っては捉える目の狩猟のようである。風景の所有、自然の所有への欲望は、19世紀にはじまったものではない。それ以前何百年もの間に絵画、特に油絵は、ヨーロッパにおいて人の万物の所有欲を反映してきた歴史がある。絵画の遠近法と額縁(フレーミング)による世界のミニチュア化、箱庭化は、西洋の植民地支配意識、権力構造を大いに担っていたが、王侯貴族や教会が支配の後、新しい時代の支配者である中産階級たちの所有願望もこれを大いに引き継ぐものであった。油絵によって可能となった所有と収集を、写真はさらに手軽に迅速にして、新興の支配者たちの願望の扉を開いたのである。
つまり彼らの支配欲は、それ以前の支配者にも増して、「所有」というものに特化していたのではないだろうか。そう仮定すれば、写真の急速な普及と量産、パブリック・カメラオブスキュラによる密室への自然の取り込みは随分理解し易くなるのである。
2-8.カメラ・オブスキュラとパノラマ
ScotlandとIrelandの間に浮かぶ小さな島、Isle of Manの湾を見渡すDouglasに立てられた家型のカメラ・オブスキュラは、写真鏡装置とパノラマ装置を共存させた、珍しいスタイルである。12角形の建物の屋根の上には12の小窓それぞれにレンズが取り付けられてあり、各小窓のレンズからほぼ360度の外界の風景を取り込む仕掛けである。(しかし開館後間もなく観客の出入りのために12角形の建物の一角はエントランスになり、12のレンズは、11に減らされた。)
1850年に開館したEdinburghのOutlook Towerのカメラ・オブスキュラは、その時点で16世紀の天文台から続く100年以上の歴史をもっていたが、Isle of Manのオブスキュラは1892年に建てられたもので、オブスキュラ装置としては応用編といったところであろうか、複数のレンズを用い建物内に映し出された周囲の風景は、暗室の中にいながらにして360度の展望台からの眺めである。EdinburghのOutlook Towerをはじめとする、典型的な単眼式カメラ・オブスキュラ(真上のレンズから小屋の中心の卓上に像が映るタイプ)とは異なり、Isle of Manのオブスキュラ内部の中心は空洞であり、卓は壁に沿って置かれていて11の像がレンズを通してそれぞれ映し出される。観客は、この小さな木造の小屋の入口で入場料を払った後は、12角形の建物の壁に沿って、すれ違うのも難しい細い回廊をテーブルを見ながら回らなければならない。レンズが取りこんだ11の風景像は、卓上で完璧につながっているわけではないので、全方位を撮影した回転式カメラ写真のようには見えないが、暗室の中の、海と山を見渡す風光明媚な景色は、やはり当時大流行したパノラマを強く意識させる。(図7参照)
カメラ・オブスキュラとパノラマは、遠近法という視覚文化で括られて語られるのが常であるが、ここでは実際に訪れたパノラマ式カメラ・オブスキュラの印象から、19世紀に一世を風靡した二大視覚装置について、いくつかの相違を述べることにする。
パノラマは、ギリシャ語で「すべてを見尽くす」という意味をもつ。パノラマ館の特徴は円筒形または多角形の建物、その内壁(カンヴァス)は高さ14メートル、外周140メートル、直径40メートル程であったという。(1830年頃の基準による)観客は巨大な建物の入口から廊下を通り螺旋階段をのぼって展望台へとたどり着くと、全方位を埋め尽くす巨大なカンヴァスに囲まれた。綿密に描かれた自然や街や、歴史的絵画と観客の立つ展望台との間には空間があり、本物の樹木や人形のセットが組まれて三次元と二次元が混ざり合って視線をカンヴァスに促す。採光は主に間接的な自然光で、屋根のガラス窓から入った日光が展望台の上方に吊るされた巨大な傘によって拡散し、カンヴァスの絵を照らして、眼も眩むような現実感に酔えるような仕掛けになっていた。(*5)(パノラマの壮大さや、車窓の風景の早さや、物の過剰さに眼も眩む、眩惑されるという現象は、いかにも19世紀的であるが、現代の視覚変革においても光癲癇症や3D酔いのような眼と脳の混乱は常に起っている。)
このような巨大で大掛かりな建造物に比べれば、Isle of Manのカメラ・オブスキュラは、実にささやかな木造小屋の視覚装置だが、構造的にはパノラマを踏襲したものである。パノラマ館の円形の展望台の上を観客がまわりながら眺めるように、Isle of Manのオブスキュラも観客たちは多角形の小屋の側面を壁に沿ってまわりながら風景を見尽くす。
同じく1900年前後に流行した視覚装置にステレオスコープがある。これは両目に視差から生じる二つの像から立体的視覚が作られる効果を利用したものである。このステレオスコープを何十も集めて大きな円筒形覗き込むような娯楽装置に仕上げたカイザー・パノラマは、今もBerlinの科学博物館に残っているが、これは円筒形、多角形の部屋の内部に入るのではなく、外壁にあいた穴を覗く仕組みになっていて見渡すという行為は不可能である。
本来、マン島の複眼オブスキュラの制作者Fieldingは、当時流行していたこれら幾つかのタイプのパノラマ館について知識を持っていたに違いなく、可能であれば、複数のレンズから取りこんだ海と島の水平と地平をひとつにつなぎ、観客が小屋の真ん中に立って島の全方位を見尽くすことが出来るドーナツ型の卓上パノラマを作るのが理想だったのかもしれない。しかし屋根のレンズを通して落ちる像は小屋の内側から見れば逆像となり、結局、観客自身が歩いて卓の周囲を回るという「回遊式」になったのではないだろうか。
パノラマ館が目指した知覚のひとつは、観客をぐるりと取り囲む「地平線」であったと言われている。視野を限界づける地平線は、地平の拡大という目標と重なり、近代的主体が目指す指針つまり「啓蒙」という概念を与えたというのである。
カメラ・オブスキュラの多くが、地平線を見るべく高台に、また「水平線」を取り込むべく臨海に立てられた理由も、軍事的監視目的という現実的役割を鑑みても、そこから推察できる。実際に、Isle of Manのカメラ・オブスキュラも二次大戦時代までその役目を担ったのである。
パノラマ(panorama)は、1792年にScotlandの画家、Robert Barkerによって作られた造語であり、パノプティコン(Panopticon)と語源を同じくしている。全て(pan-)見る(-opticon)つまり、中央展望台から一望する視点はそのまま監視装置、前章で述べたような視線の民主化と解放は、そのまま視線の支配につながるわけである。
またパノラマ絵画の細密さは、観る者に、奇妙な「静止感」と、時間のコラージュ的違和感を呼び起こしたと言われているが、部屋式カメラ・オブスキュラの中で見る像も、不思議な遠近感を持っている。すべてにピントが合ったpan focusの景色は、例えば海上の波紋の動きもどこまでも均一に見えるのである。パノラマ絵画が時間的なフラット感を持っているとすれば、オブスキュラが映すのは空間的な平面性である。
3-1.近代の視覚革命
近代の視覚は自己の視点を主軸にする事、視覚を自律させることであった。宗教や習慣、従来の美意識、各人の身体性に左右されず、視たものを客観的に認識し世界構成の確立を目指す。つまり世界をありのまま正確に捉えること、人間の身体が作り出す曖昧で不確実な視覚を取り除き、光学に基づく客観的真理の基準に基づくことである。特に16世紀後半から18世紀末までの間、カメラ・オブスキュラは世界を捉える絶対的な視点という地位を誇っていた。この機械的装置が保証する最新の科学、光学的原則を人々は唯一の真理を得る為の手段として信じており、疑う余地のない正確なものとして君臨し続ける最大の権威的視点だったのである。例えば、画家が対象物を描写する場合にも、オブスキュラの視点の基準が大きく世界観を規定した。自己の内部と客観的視点と描写が食い違ってはいけないという制約が生まれたのである。前章で述べた通り、オブスキュラの歴史は非常に古く、近代になっては特に目新しい装置ではなかったし、急進的な視覚革命を起こしたわけではない。各時代、社会の中でその役割は構成されてきたのである。
19世紀の生理学の発展により、人間の目を初めとする知覚装置、知覚のプロセス、脳や神経との関係など、分断された身体のパーツの解剖と解明が急速に行われ、人の五感も認識された。視覚については特に細密な解明がされ網膜やレンズ、視神経の伝達など眼の研究は、それまでの視覚の認識に大きな変化をもたらした。科学者は生物の眼に大いに注目し、それまで無視され、白紙、つまり「カメラ・オブスキュラの内部」のような空洞、無垢とされてきた人間の曖昧な主観的視覚は、急激に注目され存在を得、人間の視覚の可能性について様々な研究がなされるようになる。
同時に近代の自律的視点を保証してきたオブスキュラによる世界認識は、危機的な状況を迎えた。オブスキュラという知覚モデルは、人間の認識を制約してきた画一的で大仕掛けの装置として、急速に前時代的なものになっていった。(*6) 近代の視覚革命というものがあるとすれば、まさにこの「人の眼の解明」と「オブスキュラ離れ」、さらに「写真の普及」が同時に始まった19世紀前半である。
第2章で述べた、19世紀半ばのEdinburghの公開天文台とパブリック・カメラ・オブスキュラへの反対運動がこういった時代背景とどのように関係していたかは明らかではないが、「粗悪な科学的見世物」という非難の声は、オブスキュラがすでに人々に科学的な啓蒙を与えるものではなく、大衆のための娯楽という地位に移行していた事実を示すのではないかと思われる。特にスコットランドのEdinburgh は天文学や光学において遅れた田舎町ではなく、イギリスに対抗意識を燃やし、天文学者を多く輩出した一大拠点であった。
ともあれ、視点が再編成されようとする転換の時代に、オブスキュラの内部の像を写し取り固定化できる技術、つまり写真術が完成するのは興味深いことである。その後、オブスキュラやパノラマは、人工視覚装置の流行の終焉とともに次々と姿を消し、現在ではわずかに欧米の地方都市の所々にひっそりと残っている。いずれにせよ、18、19世紀の視座がまだ保存され、私たちが目にすることができる経験は貴重である。
何故なら視覚とは単に目に映るものではなく、常に社会や文化が作り上げていく世界像であり、歴史の中の視覚意識の変容を追うことは、現在まさに大変革の途上である私たちの視座を自覚するのに最も意義深いことではないだろうか。
3-2.カメラ・オブスキュラの可能性
映像文化発展の基盤を創ったとされるカメラ・オブスキュラとは、一体どのようなものなのか。現在我々が使用している写真撮影用のカメラと共通するものであるとは言っても、その実態はほとんどわからなかった。写真発明を担った装置であるとされて、どの文献資料にも同じような図版が掲載されているが実物を見た者はまずいない。実際にその内部に入って、投影される映像を見た印象や体験を語る者の話を聞いたことがない。写真の撮影カメラ、撮影者の体験などについては数多くの言説があるのに対して、カメラ・オブスキュラについての記述は極端に少ない。
そうした中にあってJonathan Crayは「観察者の系譜」などの著作で、近代思想に及ぼしたカメラ・オブスキュラの影響と役割を、多くの思想家の言説を引用して論じている。Jonathan Crayが実際にカメラ・オブスキュラを体験した上で論述したのかは明らかでないが、指摘は的確である。カメラ・オブスキュラが観測装置として果たしてきた役割の重要さは当然のことであり、デカルトをはじめとする近代思想家たちの思索の「…何よりもまず客観的真理に近づくことを保証する装置であった」(*7)のだが、見落とされがちだったカメラ・オブスキュラと人間の身体との直接的な関係についても資料を駆使して論述していることに注目したい。
太陽観測で、「ケプラーやニュートンといった[ 古典主義の] 偉人たちは、太陽や太陽光線に関する知を獲得しようとする際に太陽を直接見ることを避けるというまさにその目的のために、カメラ・オブスキュラを用いた。」(*8)そして、それまでの太陽観測では、直に太陽を見ることによって目を焼かれてしまう危険と隣り合わせだった。「太陽を直視する科学者たちの身体の上には、太陽の光が焼きつけられた。その光は身体をかき乱し、光り輝く色彩がその身体の表面に拡散していった。この時代のもっとも著名な視覚研究者のうち三人は、太陽をくりかえし凝視したすえ、盲目になってしまったり、永久に視力を損ねてしまったりした。」(*9)このようにカメラ・オブスキュラは、視覚を奪われないために人間の視覚機能の一部を肩代わりするという、視覚の身体性についての緊張感ある関係の上に成立していたのである。
そしてカメラ・オブスキュラの客観的視覚の獲得という観点に於いても、「…この暗室(カメラ)の機能は、見るという行為を観察者の肉体としての身体から切り離すこと、視覚を非肉体化することであった。」(*10)あるいは、「…かくして[ カメラ・オブスキュラのなかにいる] 観客は、[ 遠近法絵画を眺めるときと比較すれば] 再現=表象化の仕掛けからより独立した、周縁的で補足的な存在として、暗闇のなかにあって自由に浮遊する存在となるのである。」(*11 )として、暗闇のカメラ・オブスキュラ内部に展示投影された外の風景を見たときに感ずる、見る主体としてのわたしとは無関係に分離されながら、光る物質と化したような精緻な映像を眼前に眺める感覚、身体を風景に対峙させながら見ることとは異なる、客体化された映像としての風景を見るという行為の有り様を述べ、さらに遠近法で描かれた風景画を、あたかも画家の描写をなぞるかのように解読して眺める場合とは明らかに異質な、あるいは、見る行為とその身体が直に風景を前にした時には様々なノイズに遮られて感受できなかったことが、カメラ・オブスキュラという装置によって鮮やかに立ち現われる様子を暗示させるのである。
カメラ・オブスキュラ内部で生起する、こうしたプリミティブな身体と映像との出会いは、夢や幻といった人間にとって身体と分ちがたく結びついたイリュージョンの世界での現象と通底するものがある。カメラ・オブスキュラとは、覚醒していながら夢見ることを可能にした装置でもあるのだ。
カメラ・オブスキュラが近代に至るまでに果たした重要な役割、すなわち、観察者のための観測装置として客観的な視座を確保した存在意義は非常に大きなものがある。その一方で、感覚受容体としての人間の身体が視覚映像装置の内部で感受するものは、認識を手助けする視覚装置としての役割に止まるものではないのである。
映像が日常生活に氾濫し、映像に身体を浸食され尽くしているかのような現代人にとって、すでにその役割を終え過去の遺物と化したと思われていたカメラ・オブスキュラという存在は、人間と映像との初源の出会いを再確認できる場となる可能性を今もなお保持している。そして、カメラ・オブスキュラに於ける人間と映像との再度の出会いを通して、改めて新たな映像と人間との関係を模索する手がかりを見つけることも不可能ではないと考えられるのである。
注・引用文献
- *1―
- 完成年は[ カメラ・オブスクラ年代記]John H. Hammond 著、川島昭夫訳、朝日選書、朝日新聞社2000 年発行
p217-218 - *2―
- インターネット・サイトThe Astronomical Society of Edinburgh A Guide to Edinburgh's Popular
Observatory Home page http://www.astronomyedinburgh.org/publications/booklet/ - *3―
- インターネット・サイトThe Magic Mirror of Life Great Union Camera Obscura,Isle of Man 掲示の2葉のポストカードによる
http://brightbytes.com/cosite/2iom.html - *4―
- 前川修著 「痕跡の光学」ヴァルター・ベンヤミンの「視覚的無意識」について 昇洋書房2004 年発行 p107
- *5―
- 同上書 p99
- *6―
- ハル・フォスター編 「視覚論」平凡社 近代化する視覚 Jonathan Cray p53~
- *7―
- Hal Foster 編、榑沼範久訳、近代化する視覚Jonathan Cray「視覚論」平凡社2007 年発行、p57
- *8―
- Jonathan Cray 著、遠藤知巳訳「観察者の系譜」以文社2005 年発行 p205
- *9―
- Hal Foster 編、榑沼範久訳、前掲書 p61
- *10―
- onathan Cray 著、遠藤知巳訳 前掲書 p68
- *11―
- 同上書 p71