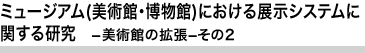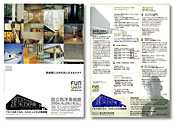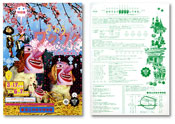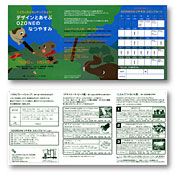![]()
Research on the exhibition program and method in the museum 2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
研究「ミュージアム(美術館・博物館)における展示システムに関する研究 -美術館の拡張-その1」においては、現代の美術館における展示内容と展示空間との関係、都市の文脈と美術館との関係を考察することを通して、アートの場としての美術館の現在を検証した。「アートの場」についてはK.シュバートによる「進化する美術館」*1に代表される博物館学(ミュゼオロジー)、美術研究の立場からのすぐれた研究が既に存在することは、近年のアートと「アートの場」が今日の社会にとって果たす役割の重要さを示すものといえる。
本論(その2)においては、「アートの場」が美術館建築の中にとどまらず、都市空間や自然の中に広がっていくとともにアートと鑑賞者の関係も多様に変化していることを示すことを試みている。従来、アートを作品として収集し、アーカイブを形成し、それを展覧会という形式で鑑賞者に提供する場としての美術館が、80年代後半からアートという資源を用いた教育活動を積極的に行ない、新たな鑑賞者の発掘あるいはアートの場の拡張を目指すようになって来た。
本章担当の鈴木は80年代後半から公共の美術館で継続的にワークショップを行なうとともに、「せんだいメディアテーク」をはじめとする拡張されたアートの場、新しい情報技術とリテラシーのプログラムのデザインを行なってきた。その経験に基づいて、近年の美術館・博物館における教育プログラムの事例調査の報告とその意義について論ずる。
(文責:岡部憲明)
| *1― | 『進化する美術館』K.シュパート 松本栄寿・小浜清子訳、玉川大学出版 2004 “The Curator' Egg" Karsten Schubert |
|---|
1)概要
美術館、博物館などいわゆるミュージアムの重要な活動のひとつに教育プログラムがある。小中学校や高校における学校教育のプログラムに対して、それは美術資料や博物資料など個別に持つアーカイブや、研究者やキュレーターなど人的資源、さらに研究調査資料など、すなわちミュージアムのリソース(資源)に基づいた各館ごとに独自の、そして高度な教育プログラムを展開できることが特徴である。
美術館、博物館はいわば専門店としての教育資源をもっているわけなのだが、その活用方法(教育プログラム)の研究はまだ端緒についたばかりである。その大きな理由は、ミュージアムは資料のアーカイブ(収集、所蔵、調査、研究)と展示や展覧会の開催が第一義であり、その知の公開や教育普及は二の次であるとの認識があったからである。
いうまでもなくミュージアムの貴重な資源に基づく専門的教育の効果は大きい。そのことに気付いた欧米のミュージアムでは、古くから独自の専門的あるいは一般・子どもを対象にした教育プログラムを実施、さらに充実させてきている。
わが国でも、1980年代の後半から新設された公立ミュージアム、たとえば目黒区美術館、世田谷美術館などを皮切りに教育プログラムの確立と普及を念頭に、組織と人材を設置する動きが出てきた。その流れと成果は、1990年代の水戸芸術館やせんだいメディアテーク構想、さらに金沢21世紀美術館の理念と活動の根幹をなすものに至っている。
本論では筆者がさまざまなかたちで関わってきた公立ミュージアム(館のプログラムデザイン:せんだいメディアテーク/ワークショップ講師:目黒区美術館、国立西洋美術館、国立民族学博物館)民間ギャラリー(OZONE)と、最近開館した公立ミュージアム(金沢21世紀美術館、英国テートモダン)のヒアリングや見学調査などに基づいて、まず、ケーススタディとしてそれぞれの美術館の個性あるアーカイブや資源に基づいた教育プログラムの概要と特色を述べる。さらにこれら教育プログラムの実践が、従来からのミュージアムのアクティヴィティをどのように広げていっているのか、その効果と可能性を述べる。
2)事例の概要、プログラム記述、特色(考察・特性の評価)
以下に今回調査した8件の事例を紹介する。各事例ごとに筆者による【概要】紹介、1:から3:までは、そのプログラム自体に特徴があることから、筆者によるヒアリング・インタビュー・ワークショップ参加、あるいはパンフレットなどに基づいて【プログラム記述】を付記した。最後に【特色】としてアクティビティの総合的考察と特性評価をまとめている。
1:せんだいメディアテーク
【事例概要】
せんだいメディアテーク(以下smt)は、2001年仙台市に開館した複合文化施設(運営は仙台ひと・まち交流財団)である。施設は仙台市民図書館(11万冊、閉架30万冊)とギャラリー(大空間と小割りされた部屋が連なる2フロア:4,800m2)、ホール(多目的な利用)、スタジオシアター(180席:映画上映に特化)、スタジオ(コンピュータなど情報機器を用いた小さなセミナーに有効)、カフェなどからなる。ギャラリーはコレクションを持たず、通常のミュージアムに所属するような学芸員は持たない。
しかし、ここでは従来の市民ホールや公民館の貸ホール、あるいは貸ギャラリーとして場所と空間を提供するだけではない。smtは、市民の文化活動や社会活動、さらに学習や情報へのアクセスをサポートする。smtはスペースを貸すのではなく、ノウハウを貸す/与える/育てるといえる。自主企画はいうまでもなく、市民グループによって持ち込まれた企画をsmtがさまざまなかたちでサポートを行い、広く市民に租借できるようなかたちにすることにある。さらにその成果とノウハウをsmtおよび市民の資産としてアーカイブ化して蓄積することを目的としている。
「企画活動支援室」と呼ばれるセクションのスタッフは、通常の美術館におけるキュレーターと教育プログラムを司るスタッフの両面をカバーし、「活動支援プログラム」の主なものは「smt協同プロジェクト」「スタジオ利用活動支援」「smtボランティア活動支援」である。ここでは特にsmtの特徴ある「smt協同プロジェクト」を以下に見てみよう。
【プログラム記述】
以下はせんだいメディアテークのホームページに記された「smt協同プロジェクト」の紹介である。
「smtと事業目的を共有する方々と連携、協力することによって、単独ではなしえない活動の広がりを実現し、日々移り変わるニーズに的確に対応しながら持続的に発展する運営をめざしています。 [smt協同プロジェクト]は、そのための取り組みのひとつです。smtとの協同によるプロジェクト推進を希望する[事業や活動]を募集し、趣旨の合致度や、協同できる範囲と効果などの観点から審査選定の上[smt協同プロジェクト]として登録して、より多様で実り多い活動や事業を創出できるような企画立案体制をを作ろうとするものです。登録後は、登録申し込み者による事業・活動のアイディアやプラン、実施のためのマンパワーなどに対し、smtは企画運営へのアドバイス、広報協力、7階スタジオの施設や情報設備の提供などの[企画協力]を行います。
<smt協同プロジェクトへの登録・参加>
smt協同プロジェクトの登録は、原則として年2回4月と10月に受け付けます。登録には、登録手続きが必要です。
<smtが提供できること>
企画や実施計画などについての学芸員による相談、協力、もしくは協力者の紹介
活動のための参加者相互の連絡や、一般への参加募集などについての手段の提供
7階スタジオの施設や設備、活動用サーバー、ロッカーの継続的使用(予約必要)
※smt協同プロジェクトでは助成金などによる支援は行いません。
※実施にあたっての当館の施設利用料の減免やスタッフの協力を前提としません。
※事業を協同開催により実施したい場合は、別途ご相談ください。」
さて、smtのもっとも基本的なサーヴィスと活動に、はじめての利用者(就学児童、中高校生、一般)に対する施設の紹介とサーヴィスを紹介するための[ガイドボランティア]というプログラムがある。ここでトレーニングを受けたスタッフによって毎月土曜日、1~2回程度、さまざまな特徴あるツアーが挙行される。以下にそのプログラムを紹介する。
「<ガイドボランティア活動>
『せんだいメディアテークを見学したい』、『せんだいメディアテークについて知りたい』というご希望に応えるため、せんだいメディアテークの施設や事業、建物の建築的特徴などについて案内する「ガイドボランティア」の活動がスタートしました。
◎ガイドボランティアの活動
smtガイドツアー :「smtガイドツアー」は、ガイドボランティアが館内各所の構造や機能をご案内する企画です。
◎smtガイドツアーこれまでの活動
2001年12月15日土曜日、22日土曜日いずれも午後2時から午後3時まで、「smtガイドツアー」をおこないました。
参加者は市政だよりなどで募集し、計9名がツアーに参加しました。
ガイドツアーは、初めに約10分間メディアテークの概要を説明し、建設の様子を説明したビデオを見ます。その後実際に館内を歩きながら施設の利用方法や建築の特徴について説明していきます。」
| *1 | 「せんだいメディアテークホームページより」(最終更新日:2002年1月26日)引用 |
|---|
【特色】
せんだいメディアテークでは活動のプログラムや展開にも利用者が関わる。いくつかの協同プロジェクトは継続的なプログラムとして、smtのアクティヴィティの柱となってもいるくらいである。また、さまざまな障害者のための情報提供は情報メディア機器を用いることでさまざまな展開が可能となることから「バリアフリー支援活動」などのボランティア活動支援が行われている。これらの成果はアーカイブ化され、館の資源となることも特徴的である。
ミュージアム・アーカイブ・それを運営するスタッフ、それら資源を享受する利用者という関係ではなく、市民の知的欲求・知的好奇心を重要なモチベーションとしてアクティヴィティの中に取り入れ、なおかつその活動の成果をアーカイブ化し、ノウハウを蓄積していくということが実践されているのである。
すでに、活動の記録は「ウェブで公開」「オンデマンド出版」などによって出版、公開されている。このような記録・出版・パブリシティ機能を当初からプログラムしているのもsmtの特徴といえる*2。
◎せんだいメディアテークホームページ:
http://www.smt.city.sendai.jp/
2:金沢21世紀美術館
【事例概要】
金沢21世紀美術館は2004年に開館した新しいミュージアムである。フラットに(平屋に)並べた大小ギャラリーを持ち、市の中心に位置するという立地に恵まれたミュージアムとして美術界、建築界の注目を集めていた施設である。
都市のなかにある公園や広場のようにだれもがアクセスしやすい計画と建築デザインだが、それだけではなく準備段階にさまざまなプレイベントを開催して、市民参加による美術展やイベントの開催、あるいはボランティア組織の形成にエネルギーを注いできたことも特筆に値する。いわゆる「箱もの」、つまり美術館の殻だけをつくり、当該地域の住民にとってその中身(活動や成果)は関心を持つものではない、という従来から批判があったミュージアムのあり方とは異なった活動への模索と準備が開館以前に行われていたのである。
2001年の「せんだいメディアテーク」以降の、新しい開かれたミュージアムの典型的な現れであると評価したい。そこでこのような活動の具体的な手法や展開を調査するべくヒアリングの機会を持った。
【プログラム記述】
開館記念展の終了間際(2005年3月17日)、週末に大きなイベントを控えた極繁忙期にも関わらず交流課・エデュケーターの黒沢伸氏がヒアリングに応じた。氏は前任地の「水戸芸術館現代芸術センター」での経験に基づき施設の立ち上げの段階からさまざまなプログラムを仕掛けてきた経験を持つ。交流課の役割と同時にエデュケーターの立場から関わった開館記念展の一連の企画について伺った(2005年3月17日)。以下はヒアリングに基づいて筆者が要点をまとめたものである。
美術館の開設準備期間で、交流・活動というより「美術館活動」の母体としての利用者(市民)組織を立ち上げた。まず建設準備段階で「友の会<の準備室>」を公募、そこには予定していた枠の十倍のメンバーが集った。そこでさまざまな活動を行い、開館後は「積極的に美術を楽しむ市民の会」というボランティア組織「ざわぁと/zwart(金沢のざわとARTと組み合わせた)」に編成替えをしていった。そのメンバーは開館後の美術館の交流や教育プログラムの実施のみならず、アーティストの作品(プロジェクト)の制作補助やさまざまなアクティヴィティの主体(スタッフ)になりえているという。
開館記念展と同時に開催された「かえっこ(藤浩志のプロジェクト)」と「となりの晩ごはん」というアートプロジェクトがある。従前のアウトリーチ的な美術館の教育プログラムより、むしろアーティストのキャラクターやインスピレーションに基づいた、パフォーマンス度の高いアートプロジェクト的な色彩を持っている。それは開館記念展のなかでの役回りとして、子どもおよび美術館に関心を持つ、アート系大学生を中心とするボランティアスタッフからはじめて、広く新美術館の活動への広範な市民の関心を引き寄せるという戦略の中に位置づけることができる。
以下に開館記念展と同時に開催された市民参加のプログラムを挙げ、その特徴とミュージアムを開くことに対する効果を見ていこう。
◎「かえっこ」
「かえっこ」は、家庭に死蔵されているいらなくなったおもちゃを使ってする活動で、子どもが美術館にそれを持って集まり、「カエルポイント」という世界共通の(?)「子ども通貨」(遊びの通貨)を用いて、子ども同士おもちゃを交換しあって遊ぶもの。美術家藤浩志によって企画運営されるアートプロジェクトである。銀行等の役回りも子どもが演じるなどして、貨幣、交換など経済システムのシミュレーションをその根本に据えたアートプロジェクトである。「不要なおもちゃ」というどの家庭にもある素材を用いて、物々交換という経済のシステムのシミュレーションに楽しく子どもを引き込む、というシンプルなプログラムが、美術に関心のない一般人をミュージアムに動員することに成功している。
◎「となりの晩ごはん」
「となりの晩ごはんプロジェクト」は開館後の「プロジェクト工房」に半年間レジデントとして滞在したヤノベケンジが、スタッフなどさまざまな機会でつながった市民の家に晩ご飯をいただきにいくというプロジェクト。地域住民とのコミュニケーションを深めるとともにヤノベ自身の金沢生活を楽しもうという意図はアートプロジェクトの範囲を超えている。美術館の主棟とは離れた別棟の「プロジェクト工房」を中心とするレジデント機能は、通常の開館時間を超えて開放されている。レジデンスの活動に自由を与えるだけではなく、市民のアクセス(バイトを終えたボランティアが手伝いによる/遊びに来る)性を高めている。ヤノベ氏の活動がこのサーヴィスに負うところは大きかったと聞く。
レジデンス・アーティストは滞在する場所に由来するさまざまな情報や歴史や文化に基づく作品をつくることが求められるが、そのシナリオは形骸化することもある。「晩ごはん」「となり」という日常的な素材やつながりを用いることで、その矛盾を乗り越えている。
◎「金沢市小・中学校&美術館連携特別プログラム/ミュージアム・クルーズ・プロジェクト」
オープニング展に市内の小学生38,000人を招待した。学校単位で小中学生が来館するので手は足りなかった。そのために40名のボランティアスタッフを補強したのだが。配付されたテキストに添付された「まるびいもう一回入場券」は、親御の付き添いを念頭においたリピータ誘導戦略である。(図1)
◎「NPOによる託児室の管理運営」
すでに「キッズスタジオ」と呼ばれる部屋で本の読み聞かせなどのプログラムをNPOによる運営で実施しているが、子連れでの展覧会入場者の子どもを一時的に預かる「託児室」の管理運営を委託することを検討中という。直接ミュージアムの活動を行うものではないが、従来、民間に開かれることのない施設の管理運営がNPOによって可能になることの意味は小さくない。
【特色】
これら開館記念展を機会に実施された数々の「仕掛け」は、通常の美術館運営や教育プログラムには見られないものである。開館記念展を機会に組まれた特別なプログラムであることは間違いなかろうが、ルーティンワークでは生じ得ない効果を生み出す。ヤノベや藤ら招聘アーティストの選択も含めて、美術館に来て展示物を見る受け身の「観客」に留まらず、施設の積極的な利用、プログラムや運営へのコミットメントを引き出し、市民(利用者)の好奇心と創造性を引き出すことを念頭においている。
もともとこの美術館は文化教育政策としてだけではなく、金沢市の都市政策の一環として企画されたという。抽象的(場所性のない)な文化政策ではなく、空洞化した街の中心部に賑わいを取り戻すこと、そしてその場所を文化創造の地とすることという明確で具体的な目標が立てられていた。
黒沢氏によれば、オープニングの前後に行われたこのような活動に敢えて「ワークショップ」という言葉で限定を与えるつもりはないという。このような活動やプログラムを教材としてストックしそれを動かしていく、エデュケーターとファシリテータをセットとして、これをコレクションとすることを考えているという。これは「せんだいメディアテーク」によるアーカイブの概念と通じるものがある。
◎金沢21世紀美術館ホームページ:
http://www.kanazawa21.jp/ja/index.html
3:テート・モダン(英国)の教員・コミュニティリーダーのための教育プログラム
【事例概要】
2000年5月に開館したテートモダンはロンドンテムズ河畔の発電所を改築して巨大な展示室を持つ現代アートのギャラリーである。近代美術のテート・ブリテンと場所を分けたテート・モダンでは作品を年代順に展示することを止め「歴史」「風景」「身体」「静物」という4つの主題で展示を行なっている。タービン室があった7階分吹抜けのタービンギャラリーでは建築的空間的な驚きと注目も集めている。しかしながら、ここではキュレーションと建築の特徴を述べるのではなく、さまざまに展開されている教育プログラムに当該館の社会へ開く姿勢を見出し、概要と特徴を述べることにする。
2005年6月、ロンドンのテートギャラリーにおける教育アクティヴィティについての現地見学を行う機会があった。テートの教育プログラムのカリキュラムはしっかりした理念と構造を持ち、あらゆる層の美術教育、美術鑑賞など、さまざまなニーズに応えたメニューを備えていることで以前から定評があった。
視察はテート・モダンのクロー・エデュケーションセンター(Clore Education Centre)を中心に行ったが、これらの教育プログラムはテート・ブリテンにおいて行われるものも含まれていることをあらかじめご承知おきされたい。以下に代表的、特徴的なプログラムをあげ、その概要を簡単にまとめておきたい(図2、図3、図4)。
【プログラム記述】
以下はセンター発行(2005年度版)パンフレットに基づいている。
◎「 TiP:Teachers in Partnership」
教員向けとして設けられたTiPプログラムは、長期に渡って現代及び歴史的美術に関心を持つ教員とテート美術館がテート美術館のリソースを用いて教え学ぶなかで、深い相互関係を築き展開するプログラムである。ワークショップの種類は以下の通りで、近代に限ったコレクション、アーカイブを持つテートモダンとテートブリテンのプログラムには特色が付けられている。
<テートブリテン>
アートと市民
ドローイングとスケッチブック
彫刻とインスタレーション
特別プログラム:人体のかたち、自然のエレメント、素材と意味
<テートモダン>
芸術と言語
芸術と社会
素材と技法
人物を描く
彫刻とインスタレーション
スケッチブックで描く
コレクションによる展示ワークショップ:ヌード/アクション/人体、歴史/記憶/社会
また、スケジュールは以下に示すように、ワークショップを終えた後、それぞれの教育現場に戻り、そのノウハウで実施し、その評価、データを携えてさらに意見交換を行うと言うように長期に渡るプログラムに基づいている。
2005年は11月4日(INSET1)に始まり、ギャラリーワークショップスとして11月8日から2006年2月23日までの火木曜日が開催され、その後、各所属校での実施を経て、INSET2、フォローアップ・プロジェクト・イン・スクール、プラクティス・シェアリングイベントなどで成果を発表、意見交換等が行われる。
参加費用は以下の通りである。
160ポンド(各校二名の参加)
◎「SCHOOL AND TEACHER REGULAR PROGRAMS」
通常の小中学校、および高校生のクラスを対象とした美術館の教育プログラム。美術館の展覧会のスケジュールに合わせてテーマが設定される。プログラムの概要は以下の通りである。
<テート・ブリテン>
ギャラリートーク(60分)、ワークショップ(90分):「私は見える」「アートとリテラシー/絵のことを話す」「特別プログラム」「ドローイングとスケッチブック」「彫刻とインスタレーション」「アートと市民」など
<テート・モダン>
イントロダクション(60分)、ワークショップ(120分):「コレクションの展示」「スケッチブックで描く」「アートと言語」「幼児のワークショップ」など。
教材は『Tate Modern & Tate Britain Teachers' Kit』『Tate Key Work Card Packs』『Resource for teachers』『Tate Britain Student Sketchbook Resource』が用いられている。
参加申し込み方法は実施日、学級グループの規模と年齢構成、希望するテーマ、活動のタイトルなどを添えて館に申し込む。その際以下のような指導教員の付き添い(学齢にたいして指導教員:生徒の比)が求められる。
5歳以下は1:5
6歳から11歳は1:10
12歳から16歳は1:15
16歳以上は1:20
なお参加生徒は費用が割引となっている。
◎「Open Tate: Professional Development Programme」
テートの美術リソースに基づいたコミュニティリーダーやサポートスタッフ(身体障害者・精神障害者やホームレス、難民、社会サーヴィス、青年団体など)のための国家資格獲得に準じた講座がある。プログラムおよび期間、経費は以下に示す。(「プログラム」:期間(経費))
「アクセステート、イントロダクション」:2日間コース(45ポンド)
「アクセステート、上級」:2日間コース(45ポンド)
「テイラーメイド、貴団体のためのプロフェッショナル技術」:(25ポンド)
◎「教員、美術教員のための夏期講座」
SUMMER INSTITUTE:5日間(180ポンド)
ARTIST TEACHER SUMMER SCHOOL:3日間(120ポンド)
◎ガイドツアー、建築見学コースなど
よりオープンなツアーのプログラムも用意されている。
【特色】
学校教育における美術教員、NPOなどのさまざまな団体における指導者など、美術教育に携わるものに対する専門的、体系的な美術館教育が、カリキュラムやテーマおよび研修期間などに応じてさまざまなコースとして設定されている。
まず、テート美術館の豊富な資源(美術、芸術のリソース)に恵まれた環境にあることを前提にこのようなカリキュラムが組まれているのだが、学校の美術教員やコミュニティリーダー主導による美術館外部で美術教育とその啓蒙に関わるさまざまな場と機会があることも条件となっている。これらの実践と環境をサポートするべく機能的にプログラムされているのが特徴である。教育プログラムは「一般」「家族向けのイベント・アクティヴィティ」「学校」「グループ」「ユース」「コミュニティグループとオーガニゼーション」といった、美術教育ニーズの場が当初から設定されていることは特筆に値する。
美術教員を対象とした長期のプログラムでは、カリキュラムの中でいったん教員が教育の現場において習得した技術を実際に試行し、その結果や成果を披露して講評を受けるという、フィードバックがあらかじめ組み込まれているのも大きな特徴である。
このような生きた(ライブな)プログラムが、一方的な教育プログラムに陥ることなく活性化させ、発展展開させていく秘訣であると思う。
◎テート・モダン、テート・ブリテンホームページ:
http://www.tate.org.uk/
4:国立西洋美術館における創作体験プログラム
【事例概要】
国立西洋美術館では展覧会に関連したギャラリートーク、シンポジウム、あるいはコンサートなどを開催するが、「ファミリープログラム」として「どようびじゅつ」、特に夏期休業中の小中学生を対象とした「Fun with collection」という特別プログラムを開催している。
筆者は昨年度の「Fun with collection 2004: 建築探検ぐるぐるめぐるル・コルビュジエの美術館」の企画とワークショップの実施に参加した。その経験に基づいて、このミュージアムにおける企画の特徴と特色を述べていきたい。
【プログラム記述】
Fun with collectionは国立西洋美術館のコレクションをリソースとして小学生(4年生程度)以上の夏期休業中の小学生および父兄を対象とするワークショップを中心とする教育プログラムのシリーズ企画である。その目的はふだん美術館に来ることのない層をひきつけ、美術の楽しさを身体で感じてもらおうというもの、いわゆるアウトリーチの活動といえる。
特にFun with collectionの特徴は、エデュケーター/ファシリテーターが企画の段階から加わり、館所蔵の絵画、彫刻の展示を資源としたかなり自由なプログラムを作成、実施することにある。
企画には外部デザイナーも加わり、チラシやポスターやハガキなどのプレパブリケーション、この企画のためのサインやPOP、パネルのデザイン企画を上記のスタッフとともに行う。以下は筆者が参加した2004年度の企画の概要紹介と特徴の報告である。
◎ケーススタディ「Fun with collection 2004: 建築探検ぐるぐるめぐるル・コルビュジエの美術館」(図5)(図6)
横溝真(建築家/東京芸大講師)と筆者は上記企画にあたり、ル・コルビュジエが設計した美術館自体をプログラムの中心に設定することとした。国立西洋美術館図書館のアーカイブの中からオリジナルの図面、ル・コルビュジエと外務省が取結んだ契約書、書簡などを調査、複写などを行い、展示物とした。
横溝氏は会場構成を担当。ル・コルビュジエの事務所「パリ・セーブル街のアトリエ」を再構成、デスクや棚を再現、壁面を復元した。また、モデュロールの寸法に基づいたクッションを制作した。
展覧会には竣工写真などとともにカッシーナ社(協賛)から、ル・コルビュジエ、シャルロット・ペリアン設計によるチェア、テーブル、ソファを展示構成した。
筆者が担当したのは2日間(二回)開催したワークショップ「モデュロールで測ロール」である。これは1820ミリの丸棒を、参加者自らの身体寸法によって目盛りをつけ、ル・コルビュジエの建築に採用された「モデュロール」を発見して、それが自らの寸法とどのような関係を持っているか、体験的に学習するものであった。
美術館の担当者は3名。外部スタッフはポスター、サイン制作等を担当するデザイナー。企画・展示の横溝真氏、およびワークショップの企画・実施は筆者を含めて3名によった。
【特色】
独立行政法人となった国立西洋美術館は限られた資源(ひと、コレクション、予算)のなかで、意欲的な教育プログラムを展開しているのは、毎回オリジナルな企画を外部スタッフ(講師)とともにデザインしているから、ということに尽きるのではないか。
上記の企画ではワークショップに筆者およびT*O(タカマスヨシコ、おくやめぐみ)、その他「ガイドツアー」として建築家(藤木忠善;建設時の現場に従事/東京芸術大学名誉教授、藤森照信:東京大学教授、松隈洋:京都工芸繊維大学助教授、岡部憲明:神戸芸術工科大学教授)などを講師とした建物見学、さらに高階秀爾(大原美術館館長、元西洋美術館館長)、安藤忠雄氏(建築家/東京大学名誉教授)のレクチャーを行ったことで、多くの建築学生の参加を得たことも付け加えておきたい。
従来からの「美術館教育」のプログラムとは異なったアプローチであり、さらに対象や領域を広げた関心と参加者を得ることが可能な企画であったといえる。
ミュージアムの教育プログラム担当者には手間がかかるが、得るところは大きいと思われる。
◎国立西洋美術館ホームページ:
http://www.nmwa.go.jp/index-j.html
5:国立民族学博物館における特別展
【事例概要】
国立民族学博物館では通常の民族学展示の企画とは異なった「特別展」を不定期に開催している。筆者は佐藤浩司教授の企画実施した「二〇〇二年ソウルスタイル―李さん一家の素顔のくらし」展(ポストパブリケーション『2002年ソウルスタイルその後普通の生活』編集)、および「ブリコラージュ・アート・ナウ…日常の冒険者たち」展(ワークショップ)に参加したことから、主に特別展という制度の特徴を報告したい。
国立民族学博物館(以下民博)は周知のように展示スペースを一般に開放する博物館であるが、大学の共同利用機関であり、組織としては研究部、大学院(博士課程)を持っている。民博の研究者は各自独自の研究領域を持ち調査研究を進めているが、博物館の一部であるスペースを用いた特別展の企画を提案する権利を有する。
佐藤教授は建築をバックグラウンドとして、東南アジアをフィールドとして民家、集落を調査研究しているが、その過程で「二〇〇二年ソウルスタイル―李さん一家の素顔のくらし」の企画を提案して実施することとなった。展覧会の詳細はここで触れないが、これは現代都市ソウルに生活する李さん一家のあらゆる持ち物、財産をリストアップして博物館で所蔵(買い上げ)するというプロジェクトの披露であった。その所蔵品は現代の日用品がほとんどであり、コンビニをはじめどこでも手に入るものである。一般的に考えられる民族学あるいは民俗学の研究史料とは異なったものである。しかしながら同時代のある一断面を正確にとらえアーカイブ化するという試みは貴重なものであった。
後者の企画「ブリコラージュ・アート・ナウ…日常の冒険者たち」展(2005年3月17日~6月7日)は、今度は民博のアーカイブ(コレクション)から、数名の外部招聘キュレーターが選びだし、同時にアートセラピーを続ける精神障害者のアート作品、ホームレスの作品と同時に展示するという企画であった(筆者は小学生とともに新聞紙によるドームを建設するワークショップを行った/2005年3月10日)(図7)。
いわゆるアートという概念を超えた、あらゆる時代、あらゆる地域の、芸術家ではないいろいろな人たちによる創造行為を同居させることによって、芸術が本来備えていた力や衝動をかいま見せることがたしかにできた好企画であった。
【特色】
民博のアーカイブは世界中の日用品がその中心であり、芸術品や歴史資料といったさまざまな評価、価値に裏付けられたコレクションばかりとは限らない。美術館における美術品のアーカイブ、科学博物館、歴史博物館などの博物館の資料とも異なっていて、基本的に見学者が手に取ることは自由である。筆者は特別の許可を得て、広大な収蔵庫を見学する機会を得たが、その量、種類とジャンルの豊かさなどに驚かされた。佐藤教授の企画のテーマ「ブリコラージュ」は、まさにこのような多彩な民族による多様なイメージと想像力によってつくられたモノの豊かさ、面白さのアーカイブに基づいているのだと納得した。
逆に言えば、そのアーカイブから価値を見出すことができるのは、既存の価値体系に捕われない観客の自由な想像力ということになる。この構造を利用した特別展の企画は現代アートの文脈と通じるものがあるのではないだろうか。
民博の教育プログラムの中で、特別展の位置づけは特殊ではあるが重要なポジションにあることはそのような理由によるし、このような試みを「美術展」「博物展」というジャンルわけにこだわらない勇気ある企画であると評価したい。
◎国立民族学博物館ホームページ:
http://www.minpaku.ac.jp/
6:目黒区美術館におけるワークショップ
【事例概要】
目黒区美術館は1987年に目黒区民センターの一画に開館した美術館である。一般の美術文化活動のための貸しギャラリー『区民ギャラリー』を併設している。当初から教育普及活動を行い、展覧会と一体となった講演会、音楽会、公開制作、ワークショップ、講師による美術講座などを行っている。
ワークショップ は「ひと」と「ひと」、「ひと」と「もの」、「ひと」と「こと」の関係性にこだわりながら、美術を通じた新しいコミュニケーション活動として、幅広い年齢層を対象にしたプログラムを、春・夏に開催している。
特に作品展示と密接に関連づけた夏の企画では多くの地域の小学生が参加している。今では開館当初の参加小学生が成人し、ボランティアでそのアクティヴィティを支えるなど、地域に根ざした美術館の特色を見せている。また、オリジナルの教材として『画材と素材の引き出し博物館』を制作、さまざまな企画の中で用いている。
筆者は当該館、教育プログラムを立ち上げた降旗千賀子氏の招聘により、数回の建築ワークショップを担当(図8)することを経験しているので、その特徴を以下に述べたい。
【特色】
◎地域の美術館の特徴を最大限に活かす
上の概要で述べた通りであるが、小学生を中心とするワークショップの参加者は地域の児童がその中心である(もちろん遠隔地より参加する児童も毎回すくなくない)。そのため、公民館的な地域の文化的インフラストラクチャーとしての機能も併せ持っている。夏期休業間には周囲の水泳プール、公民館・図書館のサービスと合わせて利用、すなわち朝子どもに弁当を持たせて、美術館のワークショップに預けて、夕方引き取りにくる、という行動パタンの中にワークショップが位置づけられる。生活の中に美術館のサーヴィス、プログラムがしっかり位置づけられているのである。
ワークショップのプログラムはさまざまである。企画展示に準拠したもの。色や画材や技法に特化したもの。あるいは地域の環境や調査に関わるものなどなど。しかし、いずれの場合も降旗氏の指導方針はゆるぎないもので子どもの自己責任を大切にしている。ワークショップの会場づくりや後片付けは子どもたちが自発的に行っている。
筆者は建築(セルフビルド)をテーマとするワークショップ(「楽しい建築教室」)を継続的(不定期)にここで開催させていただいているが、このフィールドは他にはないもので、毎回の参加者のリアクション、独特のフィールド(目黒区美術館という場所と機会)に基づいたテーマやプログラムの評価と実験を行うことに役立っている。筆者の「建築教室」というセルフビルドの建築ワークショップのプログラムはここで骨組みがつくることができた、といっても過言ではない。
◎目黒区美術館ホームページ:
http://www.mmat.jp/
7:東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園のワークショップ
【事例概要】
府中にある分館である。実物の建築を保存する博物館で小金井公園の一画にある。民俗学ミュージアムとしての独立した建築、その内部に巨大な展示スペースを持つ本館に対して、広大な野外スペースを持つ分館という位置づけから、ここには東京各地から移設された歴史的建造物が移設改修されている。
つまり、江戸東京たてもの園のミュージアムとしての資源は、実物の家や建築ということになる。同種の資源を持つ先行した施設・ミュージアムとしては「川崎市立日本民家園」があるが、前者は東京/江戸という領域の限定、民俗学的なテーマを持つことが特徴であるといえる。
いわゆる常設展にあたるものは園内にある民家、住宅などである。そして特別展はこれらの建築とは別にある本館の展示室で行われる。
教育活動は多様で、多くのイベントやワークショップは実物の建築物を用いて行われている。筆者も講師として開催するワークショップの多くは中央の広場(はらっぱ)を用いて行う(図9)。子ども向けのイベントはこのような開放的な環境(農村の、田園の集落ような)を活かした遊び、暮らし、生活などに関連した企画が多い。
一昨年開催された特別展、「千と千尋の神隠し」に因んだ「江戸東京たてもの園と千と千尋の神隠し」(会期:平成14年10月12日~平成15年8月31日)ではこのような資源を歴史、ノスタルジーといったメタファに用いて、一般にも親しみやすい企画であるといえる。
【特色】
ボランティア活動として「茅葺き民家での燻煙」「ガイド(ツアー)」「主に民俗学的なサポートなど」を行っているが、これもアーカイブとしての民家を固定化して死蔵するのではなく、常に生きた状態(動体保存)で活用する有効な方法であるといえる。
近年のまちおこし、まちづくり、まちなみ地域保存の活動の中で、歴史的資産としての建築・住宅をどのように活用し、生活の中で動体保存していくのかということが問われている。江戸東京たてもの園の多様な教育活動やボランティア事業は参考となるものが大きい。
◎江戸東京たてもの園ホームページ
http://tatemonoen.jp/
8:OZONEにおけるワークショップ
【事例概要】
東京ガスが運営するリビングデザインセンターOZONEにはギャラリースペースがあり、さらに顧客サーヴィスとして家づくりのためのセミナーなどを行っている。その活動の一環として子ども向けの教育プログラムが組まれている。筆者は一昨年度、建築家グループのみかんぐみなどと共同してセルフビルドによる家づくりのワークショップを行った(図10)。このような子どもを対象とした夏休みの企画は、新宿という地域性が薄く、民間企業によるショールーム的な色彩の濃い当該施設ではあるが、継続的な開催によって定着しつつあるように思える。
【特色】
ギャラリーの他、住宅を建てようとする一般のクライアントを対象とするさまざまなセミナー、コンサルティングの窓口、ライブラリー、さらに同じ建物内にあるコンランショップを初めとするインテリア、家具、小物などのショップなどが集約したいわゆるデザインセンターである。
他のミュージアムとは異なっていて、リソースはスタッフとデザイナーを中心にした顧客、さらに情報センターとしてのアクティヴィティのノウハウ、さまざまなショップなど商業施設のブランド力および集客力であるといえる。
英国におけるハビタブランド、コンラン財団によるデザインミュージアムの例もあるように、このようなデザインセンターがミュージアム的な展開を遂げる可能性もなくはないが、むしろ先にのべたような商業的、デザインセンター的な情報、集客装置としてのリソースで教育的なプログラムを企画し、展開している様をミュージアムは学ぶところがあると考えたい。
◎OZONEホームページ:
http://www.ozone.co.jp/
3)結論:多様な教育プログラムの実践が展示を中心に組まれていたミュージアムのプログラムとアクティヴィを広げる
前節で見てきたように現代のミュージアムは、従来からのアーカイブとその展示という固定的な活動だけではなく、多様な教育プログラムを持ち広く展開している。
その結果、専門化したリソースに関する研究や知識に基づいたプログラムに関心を持つ層だけではなく、多くの場合ミュージアムのリソースに関心を持たない人、層の関心も呼び寄せられる。むしろ教育プログラムのうち、ワークショップなどはそのような普段ミュージアムに関心を持たない層を引き寄せる企画が多く取り入れられる。もちろん、最近のミュージアムにおける教育プログラムは、より広く観客を動員する集客力に貢献したり、リピーターを増やすことを目的として高い敷居を低くすることだけを目指しているのではない。
テートギャラリーに見られるように、ミュージアムが持つリソース(資源)、すなわちコレクション、アーカイブ、ヒト、情報、機会を最大限に活用しながら、教員やコミュニティリーダーなど、想定されるあらゆるクライアントにこれらが適切に機能するようにプログラムが組まれ、そのクライアントがさらに外でそのリソースを適用し、その教育プログラムの趣旨を広げ、さらにそのフィードバックをテートが得ると言う無限の教育的循環が目指されているのである。ミュージアムの活動が広がることが、蓄積した知とアーカイブと活動の分散と拡散となるのではなく、かえってミュージアムがあらためて文化と社会の中で重要なステイタスを獲得することに繋がっていくのである。
もちろんテートの例は歴史と伝統に基づいたミュージアム技術をもとに組まれたのであるが、わが国におけるミュージアムの教育的活動も、部分的、運用的にこのような循環的教育効果を取り入れることができると思われるのである。
筆者が10年以上にわたってワークショップを行っている目黒区美術館での教育経験では、つねに講師(筆者の)の仮説に基づく教育の実践(実験)と受講者におけるリアクション、フィードバックを教育的実践の継続によって得ることが可能であった。いわば臨床的研究のフィールドとして考えることもできる場となりえていたのである。
事例として紹介したわが国のミュージアムは、十数年の教育プログラムの継続によって研究的フィールドとして育っているか、あるいはこのような前例を成果として新たな教育プログラムを開かれたミュージアムの戦略として当初から組み込んでいるなどしたものである。
わが国の「開かれたミュージアム」の核となりえる教育プログラムの実践はこのようにまだ最初の十数年を経たところにある。まだ試行段階にあるミュージアムの相互の情報交換や研究は端緒についたばかりであるが、本論で紹介したようにその多様性を最大限に評価することで、各ミュージアムのリソースの種別を問わず可能性を探ることができるし、それぞれがシェアできる教育プログラムのモデル化が可能となるのではないかと思われるのである。
(文責:鈴木明)
(注)
| *1― | せんだいメディアテークホームページより(最終更新日:2002年1月26日) http://www.smt.city.sendai.jp/ |
|---|---|
| *2― | 『せんだいメディアテーク「共有のデザインを考える/スタジオトークセッション記録」』2004年 せんだいメディアテーク活動の記録 http://archive-www.smt.city.sendai.jp/ |
(図版キャプション)
| (図1) | 『まるびぃとの遭遇』オープニング展のための教材。まるびぃは美術館の愛称。 |
|---|---|
| (図2) | SCHOOL AND TEACHER REGULAR PROGRAMMES 2004-2005 |
| (図3) | LEARNING RESOURCES FOR SCHOOLS |
| (図4) | SUMMER SCHOOLS FOR TEACHERS 2005 |
| (図5) | 「2004年fun with collection:建築探検ぐるぐるめぐるル・コルビュジエの美術館」ポスター/チラシ |
| (図6) | 「ココロのマド―絵のかたち―」 |
| (図7) | 「2005年特別展:きのうよりワクワクしてきた/ブリコラージュ・アート・ナウ/日常の冒険者たち」ポスター/チラシ |
| (図8) | 「目黒区美術館春のワークショップ2002:楽しい建築教室2」ポストパブリケーション |
| (図9) | 2002年度夏のワークショップ「楽しい建築教室」鈴木明、新聞紙のドーム |
| (図10) | 「こどももおとなもやってみよう!デザインとあそぶOZONEのなつやすみ」パンフレット、2003年 |
本論においては、美術館が美術作品を収蔵しそれを展示するという従来の機能とプログラムから、たとえば美術資料を資源とした教育プログラムというアクティビティを通してさらに利用者を美術館活動の主要な人的資源に読み替えていくという現状について、執筆担当者が関わった美術館活動を運営の側面から論じた。美術館がインタラクティブな関係に重点が置かれつつあるというこうした美術館機能の新たな変化は、収集・展示の場としてあった美術館の拡張、さらなる活性化の動力として期待されるアクティビティのひとつとして注目に値するものと思われる。
本研究は変わりつつあるアートの場の形成、その活用を建築的な視点からとらえようとする試みであり、そのためには美術館の運営と利用方法の変化を継続的に調査していく必要がある。ここ数年間にわたる調査を基盤とした今回の考察の試みをもとに、今後も引き続き調査研究をおこなっていくことを予定している。
(文責:小山明)