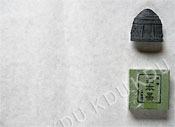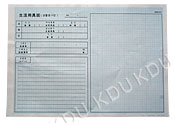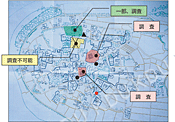本調査の宿泊地となった2ヵ所の民泊の家具と生活用具を中心に調査をおこなったのでその方法と結果について以下に報告する。
安東市河回村の生活用具の実地調査を中心に現地民への聞き取り、家具実測調査および家具装飾品拓本取りをおこなった。調査の実施に当たり事前準備物として以下のものを用意し(図5:拓本紙と拓本墨) (図6:調査記録シート)、以下の地域の記録をおこなった。(図7:調査箇所)
4-2 調査結果
調査対象とした民泊における家具数は限られており、むしろ作りつけの棚を積極的に利用していることが明らかになった。その方法は、壁内に収納スペースが施され、床空間を有効利用できるスタイルであった。実測ができた李朝系家具は以下の通りである。(図8:実測家具1) (図9:実測家具2) (図10:実測家具3) (図11:家具金具1)
コの字型鍵前面には「福」の文字が確認でき、裏面には「如意紋」の一部も確認できた。いわゆる福が舞い降り願い事が叶うようにという意味が込められており、中国の影響を読み取ることができる。魚形鍵からは、魚=陰=母体(子宮)を連想させ、多子多産の思想を表している。(図12:家具金具2) (図13:家具金具3)
ここに示す装飾的な李朝系家具は、結婚に際し嫁入り家具として準備し、いずれも村外で購入もしくは村外の職人に作らせたものであり、河回マウル独自のものは存在しなかった。
4-2-1:室内空間
広さは日本の3畳間から4.5畳、6畳、8畳間などの広さを持った各部屋があり、儀式祭礼の折りに部屋間の可動式建具を取り払えば大広間がつくれる点も日本とよく似ている。オンドル式暖房装置が付いている点を除けば、柱構造の家屋、少ない家具、濡れ縁、蚊帳の活用、紙素材の引き戸など、日本の地方農家に点在する家屋と、素材や作りにおいて見間違うほど近似している。(図14:生活空間1) (図15:生活空間2) (図16:生活空間3) (図17:生活空間4) (図18:生活空間5)
4-2-2:家具と什器類
農業の副産物としての藁素材の生活用具類も、我が国と同様に多くつくられている。籠類、縄類、蓑、鍋釜用の敷物類、座布団類など、手作りの味わい深いこれらの藁製品は農閑期の副業として農民自らが自作をしていたということである。(図19:藁細工)
縁側の天井裏を利用して乾燥保存されている漢方薬類も、その素材は彼らの生活圏から採取した薬草が中心であり、各家庭で代々受け継がれてきた知識によって受け継がれているものであろう。日本でもごく一般に見られた家庭常備薬の作り方、保存の仕方と同じである。(図20:家庭常備薬)
住居、馬屋、作業場、離れで囲まれた中庭に井戸がある点も、その平面配置や造作の方法などにおいて、基本的には我が国の農家とよく似ている。跳ね上げ式の建具などは夏の暑さを凌ぐための工夫であり、我が国でも似たような建具を確認することができる(図21:跳ね上げ式建具)。唯一異なるのは、中庭の一角にキムチ瓶のスペースが確保されていることである。これらの瓶は現在でも活用されていて各家庭独自のキムチが生産され、各々の家庭で消費されるのを原則としている。(図22:キムチ瓶1) (図23:キムチ瓶2)
以上のように家具什器類をはじめとした食料や家庭薬など、それらの種類や作り方など、我が国の農家でもおこなわれていた内容とよく似たものが多い。現在は観光土産として河回村以外の地でつくられて持ち込まれている品も数多く確認できるが、僅か30年ほど前までは殆どが河回村の中で生産され消費されていたものであろう。
4-3 小結
生活様式と家具の関係に注目すると、中国と韓国、日本の間には隣国でありながら興味深い相違が見られる。中国は、椅子座・寝台のスタイルであり家具の存在無しでは立式空間の機能化は成し得ない。その結果、古くから文明の栄えた中国は家具の様式においても世界に多大な影響を及ぼした「明式家具」(明時代1368~1644)を有している。日本は、床座のスタイルであり、床材に柔らかく平滑でない厚畳を採用したことから、置き式の実用的な日常の家具に多様な発達は見られなかった。収納も建築化された装置が多く、畳上に置かれるものは限られていた。韓国は、日本と同じ床座のスタイルでありながら、オンドルの普及により堅くて平滑な床を持ったため箪笥、卓子類を中心に家具が発達し、「李朝家具」として完成された様式を築いている。
一定階層以上の伝統的な韓国住宅は基本的に母屋と舎郎屋から成っている。母屋は主婦の部屋であるアンバンを中心に女性と幼い子供が暮らし、閉鎖的であった。舎郎屋は、主人の部屋であるサランバンを中心に男性が暮らし、開放的で社交の場であった。舎郎には儒教的な節制の効いた卓子や書架類が配され、母屋には、箪笥、箱類を中心に美しい木目の材に金物で装飾した一般的な様式に加えて螺鈿細工の華やかな家具も置かれていた。
河回村では、家具は生産されておらず近隣の都市部で購入したり、職人を呼び寄せて誂えることが一般的であったようだ。
今日の一般的な韓国の住宅ではライフスタイルの変化により、上記のような定型化された決まり事は失われつつあるが、河回村では現在でも基本的な約束事は保持されていると思われた。「李朝家具」は、日本の民芸運動の創始者の一人である柳宗悦が「用の美」の高度な例として讃え、私たちの生活上の美学にも影響を与えている。河回村の生活空間は活きている実用の様式美として更なる調査が期待されるものである。