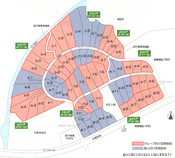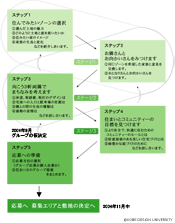本章では、みついけプロジェクトのコミュニティづくりについて言及する。みついけプロジェクトでは、入居者の募集に際し、全68区画のうち40区画において、グループ募集方式が採用されている。第1節においては、グループ募集についての説明と目的、そしてプロセスについて、第2節ではその経過について言及する。
3-1 グループ募集とグループワークショップについて
3-1-1 グループ募集及びグループワークショップとは?
「ガーデンシティ舞多聞」みついけプロジェクトの全68区画は、「向こう三軒両隣」を基準とした、a,b,c,d,e,f1,f2,gの8つの最小単位のコミュニティを構成している。居住者の募集に際しては、居住希望者があらかじめグループを形成し、そのグループの単位で応募をする「グループ募集システム」を、全68区画中40区画において採用した。残りの28区画は通常の個別募集方式が採用された。(図3-1)
グループワークショップは、そのグループの形成を促進するために行われた。ワークショップでは主に「どんな家に住みたいか?」「どんなまちに住みたいか?」「どんな環境に住みたいか?」の3項目について話し合われた。これは公開講座やワークショップにおける「住宅」「コミュニティ」「自然環境」という3つのテーマと連動している。各グループはその内容をまとめたものを「グループ協定書」として応募の際に、グループの代表者を定めた上で提出することが義務付けられていた。
なお、当初は全区画においてグループ募集システムが採用される予定であったが、都市機構における「平等原理の遵守」に照らし合わせた結果、各グループの約3分の2(40世帯)をグループ募集で行い、残りの約3分の1(28世帯)を通常の個別募集で行うことが決定した。また、1つのグループに複数の応募があった場合はそれらの間で抽選が行われることも決定した。
3-1-2 グループ募集の主旨
グループ募集システムは、現在の日本の住宅地で繰り広げられているコミュニティの形成過程に対する疑問視から、その一つの解決法として提案された。
現在の日本の住宅地は一部コーポラティブ方式などを除いては、ほとんどが抽選によって居住者の選別が行われている。しかし、この方法では各住民は入居後にそのコミュニティの構成員や環境条件などを知ることになり、そのことが持続可能なコミュテニィづくりの妨げになっている。
「みついけプロジェクト」では、グループワークショップにおける意見交換や現地ワークショップにおける共通の体験などを通じた上で、あらかじめ人的コミュニティを形成し、それを育んでいくことで、持続可能なコミュニティを実現できるという仮説のもと、このグループ募集システムが提案された。
3-1-3 グループ募集のプロセス
各宅地・グループは、立地条件や面積などにおいて、全く違う個性を持ち合わせている。居住希望者はまずその区画・グループの空間的な特徴と自らのライフスタイルを照らし合わせた上でグループづくりの第一歩を踏み出すことになる。(図3-2~5)
ここでグループ募集のステップを示す。(図3-6)
それぞれのステップはフィードバックしながら行う。なお、ステップ1・2の流れをステージ1、ステップ2・3の流れをステージ2とし、ステージごとに2度のグループ別ワークショップを行う。2つのステージを終了し、ステップ4と5をクリアした後、募集エリアと敷地を決定し応募へと備える。
また、各グループはその間に複数希望者のいる画地の人数調整、希望者のいない区画の補充、グループの代表者の選出などが求められている。
3-1-4 グループワークショップの流れ
グループワークショップのテーマは主に「こんなまちに住みたい」「こんな家に住みたい」「こんな環境に住みたい」の3項目とし、ユーザーのコミュニティ・住宅・自然環境に対するイメージの引き出しと整理を行っている。
参加者はまず、スタッフからの説明の後、グループごとに分かれる。各グループには都市機構と神戸芸術工科大学から1名づつがサポート及び記録係として配置されている。自己紹介の後、参加者にはそれぞれ付箋が配布され、設定時間内に上記3つに関するコメントを記入する。それらをテーブルの中心に置かれている模型や模造紙にテーマ別に貼り付ける。進行役がそれらを話し合われた内容に基づき分類し、そのグループ及び構成員の個性や傾向を確認しあう。それらの結果はワークショップ終了後、全グループが集合した時にそれぞれの進行役によって紹介され、今度はグループごとの個性や傾向を知ることとなる。(図3-7、8)。
3-2 グループ募集の実践
3-2-1 グループワークショップ(ステージ1、2)
2004年8月1日、2日、7日にグループワークショップのステージ1が(76世帯159名参加)、8月21日、22日、26日にステージ2が(83世帯143名参加)が、神戸芸術工科大学大学院棟で開催された。(図3-9)
ステージ1と2を通じて、コミュニティを形成でき、応募への足掛かりを得たグループは2グループにとどまり、その他のコミュニティでは構成員が不足或いは超過していた。また、多くの世帯が希望画地及びコミュニティを決めかねており、居住環境を確認するための現地見学会の必要性が指摘された。
しかし、ワークショップで行われたディスカッションは、ステージ1と2とを比較すると、ステージ1においては、「建築」「コミュニティ」「みどり」についての漠然としたイメージや要望に留まったのに対し、ステージ2においては「建築」に関しては、個々の建物のイメージから様式、機能、建材、建物の位置、駐車場、「コミュニティ」に関しては、コミュニティのあり方、ルール、防犯、ペット、歩道、「みどり」に関しては、隣地境界の生垣、街路樹、みどりの管理、オープンスペースの提供、など、広範且つ詳細な内容に及び、参加者の居住環境に対する意識の向上が伺えた。
3-2-2 現地見学会、最終のグループワークショップ
2004年10月31日と11月7日の2日間、造成中の現場の見学会が行われ、それぞれ93組(初参加24組)187名、75組(初参加39組)156名の参加者を得た。(図3-10)
この見学会はグループを決定する前に計画地を確認したいという参加者たちの強い希望により、都市機構が例外として現場への立ち入りを認めたことで実現した。参加者はそれまで造成された計画地の様子を200分の1の模型とコンピューターグラフィックスによって確認していた。
現場周辺は当時の段階でほぼ完成時に近い状態になっており、参加者は周辺部も含めた計画地の居住環境を確認することができた。また、そのことよってグループを決めかねていた参加者にも決定を促すことができた。また、現場を確認することによって、それまで加わっていたグループから別のグループへ変更する参加者もいた。希望するグループに対しては見学会終了後の話し合いの場として、神戸芸術工科大学大学院棟の施設を提供した。
この見学会以降はグループ形成が加速され、2004年11月20日に最終のグループワークショップが行われた。(参加者70組(初参加5組)111名)このワークショップをもって8グループ全てにおいてグループが形成された。(図3-11)
3-2-3 入居者募集・入居者決定へ
2004年11月27日から12月19日、「ガーデンシティ舞多聞」みついけプロジェクトの入居者の募集が行われた。グループ募集は12月5日、個別募集は12月19日にそれぞれ抽選が行われた。
期間のうち、応募者の集中が見込まれる各抽選日が含まれる毎日曜日は神戸芸術工科大学本館ギャラリーが受付会場となった。(12月12日のみ試験のため近隣の施設が代用された)ギャラリーには公開講座開催時と同様、地形模型、住宅模型、住宅モデル提案集、完成予想図(CG)、田園都市レッチワースの概要や現在までのプロジェクトの動きを紹介したパネル等が展示された。また、当日はギャラリー前からマイクロバスを定期的に運行し、現地の見学会も行われた。
グループ募集では、c,e,f1,f2の各グループにおいては複数の応募は無く、自動的に当選が決定したが、それ以外のa,b,d,gグループにおいては2~4件の応募があり、公開抽選(回転抽選機)によって居住グループが決定した。
個別募集では、募集区画20区画に対し412件の応募があり、1区画当たりの倍率は6~67倍、平均倍率は20.6倍となった。これは募集に際し、神戸市域を中心に配布された新聞折込広告による宣伝効果である。また、募集の際には応募資格として「舞多聞倶楽部会員であること」が示されたが、募集会場において応募直前に入会することを可能としたため、実際は誰もが応募できる仕組みとなっていた。なお、グループ募集で落選した世帯は引き続き個別募集に応募できる措置が取られたが、この再チャレンジで当選した世帯は無かった。また、継続的に公開講座や現地ワークショップ、グループワークショップに参加している世帯の中で、希望する画地が個別募集の対象となっていたために、当初から個別募集で応募すると表明していた世帯もあったが、ここからは3世帯が当選した。(図3-12)
3-2-4 入居者の辞退
2005年2月、aグループの当選者(グループ)が辞退した。第1補欠グループが繰り上げ当選。辞退したグループは継続的に公開講座やワークショップに参加していた他のグループとは違い、みついけプロジェクトの主旨を理解できないままに応募していた。
また、2005年6月にはgコミュニティのグループ募集のエリアで1世帯の辞退者が出たが、空き画地の補充はグループ募集の構成世帯に一任され、その結果、コミュニティワークショップに継続的に参加していたが、個別募集に応募して落選した世帯が新しい入居予定者として決定した。
3-2-5 宅地引渡しまでのコミュニティワークショップ
居住者の正式決定(2005年2月)から宅地引渡し(2006年4月)までは、神戸芸術工科大学が主体となりコミュニティワークショップ(後述)が行われている。これは全ての居住予定者に参加が義務付けられている。ここでも引き続き「住宅」「まちなみ」「自然環境」についての話し合いが行われ、良好なコミュニティを目指すべく、デザインコードやコミュニティマネージメントのスキームなどを構築して行く。